
何十年もの間、建物のライフサイクルは、計画、設計、建設、解体、そしてもちろん、この歴史における大悪役である埋め立てという単純な公式でした。時間が経つにつれ、建築実践では再利用、解体、循環解体などの概念が取り入れられるようになりましたが、多くの場合、二次的な要素として、建築における循環経済への徐々に移行する一環として行われました。しかし、これらの原則がもはや例外ではなくなったらどうなるでしょうか?本来の用途を超えた価値や目的を維持するために、すべての建築コンポーネントを作成または選択したらどうなるでしょうか?真実は、解体後にも生活があるということです。この移行は、解体から、再利用、再利用、持続可能な解体に重点を置いた実践への移行であり、現実に近づきつつあります。 2030 年が到来するまでに、プロセス、構築、市場そのものへのアプローチ方法を根本的に変えることができるでしょう。こうした変化が展開するにつれて、私たちは持続可能性に関連する進化する目標や課題、そしてもちろんそれらがもたらす新たな機会に当社の戦略がどのように適合しているかを評価する必要があります。

持続可能な開発目標(SDGs)と国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)に関連する決議については多くの議論が行われており、これらの決議は新たな目標を提案し、しばしば困難なシナリオを提示しています。これらの決議は、先進国の優先事項によって形作られることが多いですが、多くの人々の当面の現実、日常生活、人間のスケールから切り離されていると感じることがあります。これを踏まえ、建築家やデザインスタジオは、具体的な取り組みを実施し、より人々に近い規模で新たな機会を特定するという課題に直面しています。材料の解体や再利用などの行動は、資源が豊富な地域であっても、再利用がオプションではなく必須である地域であっても、さまざまな状況において実行可能で一貫した代替案を提供します。
業界の進化する性質を考慮すると、多くの建築基準とプロセスが間もなく変更され、材料管理と商品化の新たな機会が生まれる可能性があります。資源不足が深刻になったり、未使用の材料に対するより厳しい規制が課されたりした場合、建築家やデザイナーは既存の建物を貴重な鉱山に変える可能性があります。最終的な結論は出ていませんが、これらの新しい力学が未来を再定義し、設計順序を逆転させる可能性があります。この記事では、考えられるシナリオを検討し、これらの変革が私たちにどのような影響を与える可能性があるかを強調します。

循環設計と建設の未来を形作る政策と規制
取り壊しには多額の資材コストがかかり、特に手頃な居住スペースが不足している大都市では、マイナスの社会的影響が増幅する可能性があります。この現実に対応して、「再利用の権利」を主張するという説得力のあるアイデアが注目を集めています。この取り組みはヨーロッパで具体化されており、公共政策の変革を促す可能性があり、改修と材料の再利用が最前線に置かれています。そうすることで、公共建物と民間建物の両方の可能性を最大限に引き出すことができます。
これらの変更は、新しい素材の終わりを示すものではありませんが、プロジェクトの場所と使用される素材の起源との関係を変えることになります。トレーサビリティは基本的な柱となり、各製品の経路をその供給源から追跡できるようになります。さらに、マテリアルパスポート(その特性と再利用の可能性を文書化したデジタル記録)を導入することで、この情報を体系的なツールに変えることができる可能性があります。これらのアプローチを公共政策に統合すると、建設における持続可能性が強化され、循環経済の原則に沿った責任ある実践が促進されます。


分解における最新のテクノロジーとプロセス
解体を考慮した設計が、建築環境内の持続可能性を促進する上で重要なプロセスとなっていることが確立されています。このアプローチは、回収と再利用のためにコンポーネントを慎重に分離することに重点を置いています。多くの分野と同様に、テクノロジーは重要な役割を果たしており、新たな革新技術が解体実務を形成しています。その一例は、分解作業を正確に実行する高度なセンサーを備えたロボット システムです。これらのシステムは、手動の方法と比較して精度と注意を高めて材料の回収を最適化します。

正確かつ迅速な解体作業の極めて重要な拡張は、パビリオンや仮設構造物向けの持続可能なソリューションとして確立されており、大規模な建物でも成長する可能性を示しているゼロボンド建設システムに見られます。これらの実装により、循環経済の原則に沿って、コンポーネントの再利用が促進されながら、組み立てと解体の方法が簡素化されます。デジタルツインなどのテクノロジーにより、分解プロセスの正確なシミュレーションと計画が可能になり、より効率的な資源回収が可能になります。一方、分光分析や RFID タグなどの高度な材料識別およびタグ付け技術は、すでに化学産業や物流業界で採用されており、材料の分別、追跡、リサイクルが大幅に向上し、より合理化された正確な廃棄物管理および追跡プロセスが容易になります。
材料回収プロセスを強化すると、時間の経過に伴う材料の劣化をどのように管理するかという問題も生じます。再利用できる量を超えて回収した場合、またはコンポーネントの特性が陳腐化するまで劣化した場合はどうなるでしょうか。材料パスポートに収集されたデータは、部品の状態を追跡し、検査と修理の取り組みを導き、将来の使用を予測する上で鍵となる可能性があります。さらに、デジタルツインは(分解の最適化に加えて)これらのコンポーネントを他の建物のどこにどのように統合できるかを予測し、より効率的かつ迅速な再利用に向けた戦略的な措置を講じます。

再利用と環境責任を中心とした建設とビジネスモデル
環境への責任とビジネスチャンスは両立可能な概念です。おそらく重要なのは、適切なバランスと適切な条件を見つけることです。回収された製品の仕分けと管理に焦点を当てた新興産業には、驚くべき可能性があります。材料の循環性に特化したスタートアップ企業が出現しており、これはまさにこの道の始まりに過ぎません。これらの企業の中には、2022 年のアート ビエンナーレの場合と同様に、素材を記録、在庫管理、会計するための方法論やツールを開発した企業もあり、そのリソースは翌年のヴェネツィア ビエンナーレのドイツ パビリオンで再利用されました。特に建設分野における持続可能なソリューションへの需要の高まりを考慮すると、構造物やコンポーネントを含む建物の再利用の可能性を分析することは、すぐに一般的な手法になる可能性があります。
材料の回収と分別に焦点を当てた新しいビジネスモデルを開発することで、コンポーネントを効率的に評価、分解、文書化する技術を専門とする企業の統合が促進される可能性があります。この分野のイノベーションは、リソースの売買、交換を容易にする製品カタログを備えたデジタル プラットフォームにもつながる可能性があります。新しい市場アプローチは単独で出現することはできません。それには、公共政策の変更とプロセスを最適化するテクノロジーの導入が含まれなければなりません。これらの取り組みを組み合わせることで、責任と持続可能性のバランスをとった建設および建築のビジネス モデルへの道が開かれる可能性があります。
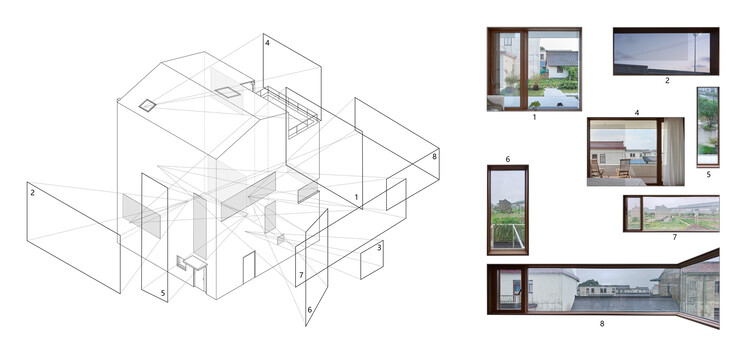

長期的には、(あまりにも多くの場合)最初の本能が破壊することである場合、環境にプラスの影響を与える環境をどのように作成できるでしょうか?持続可能な建築に向けて前進するには、破壊よりも保存を優先するという考え方の継続的な変化が必要です。解体は最も簡単な解決策のように思えるかもしれません。ほんの少しの機械と時間で、何年もかけて建てたものを消し去ることができます。しかし、それを唯一の選択肢として選択する前に、次のことを自問してください。
もし家を取り壊さなければならなかった場合、いくらで救出できますか?








